でもその先に意味を見出すことが可能なのかどうかはわからない。 デルヴォー自身がいくつもの物語を持ち、様々な構図と色でそれを描き、我々はその中に自分自身の世界を映し出す。そして自分が有する世界の中の欠落した部分を埋め、同時に自分の中の世界を広げようとする。 ただしそこでは、我々は打ち捨てられ、置き去りにされ、孤独であり、語りかけてくれる人も、振り向いてくれる人もいない。呼びかけたとしても答えてくれる人はだれもいない。 その孤独な世界に意味を見出せるのは、自分自身でしかない。 “Barbara Emerson(1985).DELVAUX,Mercatorfonds”の訳本。 画集というよりも彼の辿った歴史の全てと言ってよい。すでに絶版となり出版社もなくなり入手も困難なので、章の題名と一部の内容・感想を簡単にご紹介します。『第1章 幼年期の風景』『第2章 青年芸術家』 内向的で人との関わりが難しかった青年時代の様子が説明されている。絵に出会わなかったとしたら危なかったのではないだろうか。『第3章 表現主義の方へ』 ルージュ・クロワートルの多数の絵を「焚書」した後、不安で寒々とした後期印象派(本書での分類)的画風から表現主義へと一変し、人間を力強く描き始める。ただし孤独の予感はすでにその中に表現され、また後のシュルレアリスム的世界を先取りした作品も描いている。『第4章 長い思索の後に』 1929−1930年に開かれたスピッツネル博物館での体験が与えた影響が説明され、その後年、1934年に「ミノトール展」においてキリコ、ダリ、マグリット、エルンストの絵に出会う。そしてその同じ年に描いた「スピッツネル博物館」によってこれまでの表現主義から明らかな形で離れていく。『第5章 シュルレアリストたちとともに』 1936年の「薔薇をとる女」から、1938年の「眠れる町」と「挨拶」まで。『第6章 不安な町−戦争中のブリュッセル』 1937年と1938年のイタリア旅行以降、建築が絵の重要な構成要素となり、その後の絵の題にしばしば「町」という言葉が使われるようになる。「不安な町」はヒトラーによるベルギー侵略の数日前に書き始めたもの。 1939年の「ノクターン」から1942年にかけてオットー・リーデンブロックが登場する。同じ時期ブリュッセルの自然博物館に通うようになり、そこで彼を引きつけたのは人間の骨であり、1943年頃から骸骨を描き始める。『第7章 解放』 1944年にポストキュビズムの作品を見て大きな影響を受け、彼の画風には明らかな変化が表れ、「階段」のような扇形に広がる多角形の網の目を使った、複数のパースペクティブの重なりを作り出すことになる。『第8章 夕べの列車』 1950年代に入ると骸骨が絵の中心となる。また、以前から書かれていた列車や電車は特別の意味を持つようになり、その後「夜の小さな駅」で代表されるノスタルジックな作品へと変化し、さらにエミール・ランギが『日常性が魔術的な現実性を纏っている世界』という「冬の夕べ」が描かれる。 また50年代から60年代にかけては、郊外の風景が描かれ、そこには多くの場合裸婦が登場し、夜の郊外を描く作品群ではランプがその人物を照らし始める。 さらに“女友達”は「階段」で絵の端に現れ、「アンティノウス」以降、本格的に描かれることになる。『第9章 海が近い』 海が描かれた1964年の「別れ」から、この本の原著が発刊される1985年まで。 「別れ」の中で、女は手を挙げて男を呼ぼうとしている。しかし男は背を向けて立ち去ろうとする。でもどこへ。 人と人とを隔てる深淵は普遍的であり、日常として我々の隣に横たわっている。そしてそのテーマにより、次第に女たちは本来的に有する生命力を失っていく。男たちは初めから、現実を実感して生きてはいない。 1966年以降の作品に登場してくる女性はダニエル・カネールという人をモデルにしたもので、デルヴォーとの仕事を始めたころ、美術史の学生で貧乏で金がなく、極端に痩せていて、デルヴォーは彼女のためにチーズや果物をそっとそばに置いてくれたとのこと。ダニエルのデルヴォー評が面白い。『第10章 シュルレアリスト』『第11章 ポール・デルヴォーの流儀』 影響を受けたペルメーク、アンソール、キリコ、アングル、プッサン、ウッチェルロ、クラナッハなどに触れ、デルヴォーと他の画家たちとの類似性や独自性にも触れ、またルネッサンスからマニエリスム、フォンテーヌブロー派などのヨーロッパ絵画の潮流の中での位置づけをする。『第12章 ポール・デルヴォーの世界』 解釈されることを拒む画家として、何故彼は解釈されるのを拒むのかを説明しようとする。デルヴォーは我々が普遍的に孤独であることを描いている。それと同時に、我々に対する希望も持ち続けていたようである。 詳細で重厚な一冊。日本で発売された四冊の画集のうち、最後に読んだ方が理解しやすいと思います。 デルヴォー画集 関連情報
パリ・オペラ座のライヴです。画質はいいとはいえませんが、ベルガンサ、ドミンゴ、ライモンディ、リチャレッリ すばらしいキャストです。ドミンゴ、ライモンディはミラノ・スカラ座、ウィーン国立歌劇場でも、何回も競演しており、フランチェスコ・ロージー監督の映画「カルメン」でもすばらしい歌唱、演技をみせています。ピエロ・ファジョーニの演出は、ドン・ホセの心象風景が挿入され、必ずしもオーソドックスとはいえませんが、奇をてらいすぎていない、基本をおさえたわかりやすい演出になっています。国際的スターで主要登場人物をかため、脇はフランス出身の舞台経験豊かなヴェテランでかためています。パリ・オペラ座のフランスオペラは、一見の価値があります。 ビゼー:カルメン [DVD] 関連情報
 ポール・デルヴォー 〔骰子の7の目 シュルレアリスムと画家叢書〕 (シュルレアリスムと画家叢書 骰子の7の目)
ポール・デルヴォー 〔骰子の7の目 シュルレアリスムと画家叢書〕 (シュルレアリスムと画家叢書 骰子の7の目)
作品の数は60余り。白黒のものがあること、絵の全体とその一部分とが重複して掲載されている作品があるのが残念。部分の細部を説明しているということでもないので、スペースがあるのであれば別の作品を載せて欲しかった。 6章から成り、題の意味は「POST−SCRIPTUM」に書かれている。またそれぞれの章の最後に“純粋な解説”とは言えないような、デルヴォーの絵によってインスパイアされたと思われるテクストが書かれ、不思議な印象を与える構成と内容になっている。ビュトールの「ポール・デルヴォーの夢」の雰囲気に近いものがある。 目次が無く全体像がわかりづらいため、それぞれの章の題名とページ、若干の感想を書きます。・「物の秘密と雰囲気の表現」p4 この章の最後は著者と画家の対談が載せられ、デルヴォーが影響を受けたアンソール、キリコ、マグリットについて、少年の頃に見た汽車や電車について、繰り返し読みふけったジョルジュ・ヴェルヌについて語られる。ヴェルヌの「地球の中心への旅」の中の登場人物はデルヴォーの絵の中に繰り返して描かれることになる。・「待望の森の広場に」p18 新印象主義(本書での分類)からスタートし表現主義を経てシュルレアリスム的世界へ入っていく過程を解説している。デルヴォー自身はシュルレアリスムから距離をおいていたらしい。・「空しくも、不毛にもあらざる、されど大胆さに欠けた女人たち」p28 これは二つに分かれ、「立ち止まった大きな女人たち」と「実用の仕事をはなれて内気な彼女ら」から成っている。解説として、正装した男たちが描かれている理由が述べられ、デルヴォーが言う単なるコントラストとして以外の意味を探ろうとする。・「似ることによりさらに美しく」p46 モーニングを着こんだ男と裸の女の対比を言葉にしようとする。女は魅惑的である。男と女の間にある孤独と沈黙、あるいは男と女それぞれの中にある孤独と沈黙。・「待ちこがれての涙」p56 電車と駅のイメージ。これもデルヴォーの絵の解説というより、電車と汽車についての著者の創作に近い。・「死の領域に君臨する」p64 骸骨のイメージ。 “人はもしかすると、他者とは理解しあうことができないかもしれない。したがって人は、自分としか対決できないのかもしれない。骸骨の隣で裸の女が手を挙げて呼ぶ。でもだれを。そしてそれはとるにたらないことなのだろうか。” この後に「大きな人魚たち」が見開きで、エリュアールの「流謫」の最後の一行も見開きで、そして「鏡の女性」が載せられている。 図版のあとに、「BIOGRAPHIE」、「BIBLIOGRAPHIE」、「FILMOGRAPHIE」。その後にある巌谷國士による「POST−SCRIPTUM」の中でエリュアールの「流謫」と、この本の各章の題名の関係が説明されている。 最後に栞がおしゃれな雰囲気で挿まれ、瀧口修造の「隣り合う女たち」という小論が載せられている。 ポール・デルヴォー 〔骰子の7の目 シュルレアリスムと画家叢書〕 (シュルレアリスムと画家叢書 骰子の7の目) 関連情報

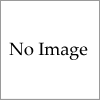




![唐津くんち[Hi-res/4K SAGA] 唐津](http://img.youtube.com/vi/ychHrwk12BA/2.jpg)
















![【Amazon.co.jp限定】KUROBAS CUP 2015 (オリジナル三方背ケース付) [Blu-ray] 【Amazon.co.jp限定】KUROBAS CUP 2015 (オリジナル三方背ケース付) [Blu-ray]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B017NJ69DW.09.MZZZZZZZ.jpg)
![劇場版デート・ア・ライブ 万由里ジャッジメント [Blu-ray] 劇場版デート・ア・ライブ 万由里ジャッジメント [Blu-ray]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B017H6ICYK.09.MZZZZZZZ.jpg)

![ワンパンマン 1 (特装限定版) [DVD] ワンパンマン 1 (特装限定版) [DVD]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B015ZAEGQ8.09.MZZZZZZZ.jpg)

![西田麻衣 Mai Boy [Blu-ray] 西田麻衣 Mai Boy [Blu-ray]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B015YLRVI8.09.MZZZZZZZ.jpg)