
シカゴで、大規模な列車爆破事件が発生。
米軍は、被害者の「死の直前8分間の記憶の残像」の世界に侵入、捜査するミッションを発動していた。
冒頭、列車の中で目が覚めた主人公は、記憶が無く、鏡や窓に映る見覚えのない自分の顔に戸惑っていると、突然列車が爆発し炎に包まれてしまう。
この導入部が上手く、一気に引き込まれてしまいます。
主人公に感情移入して観ていると、彼と同様に、夢の中のヒロイン、クリスティーンを演じるミシェル・モナハンに、非常に惹かれていきます。
目が覚めると必ず目の前に座っている彼女が、とても魅力的です。
しかし、その世界の中で人を救っても、あくまでも記憶の残像の中で動いているだけなので、そこで何をしても現実の世界には全く影響しない。
このジレンマに、これを繰り返すうちに、主人公は追い詰められていき、そしてこのシステム(手段)の極めて非人道的な仕組みに気付いてしまう。
彼は、いったんは絶望するが、それでも出来ることがあるはずだと言い…
この先が、本作の本領、テーマ、魅力です!
前向きで(でもご都合主義っぽくなく)、イイ感じで観終われるのがとっても良かったです。
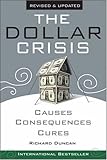
著者のR.ダンカンは、いずれ近い将来、ドルの信頼が失われ、その事が引き金となり、
世界不況が始まるという。なぜならば、アメリカの経常収支赤字が年間5,000億ドル、
累計で2兆3,000億ドル(日本円で270兆円)という史上最大の不均衡がこのまま
未来永劫続く事はありえないからだ。輸入超過大国のアメリカという存在により、
貿易黒字国は決済通貨である外貨ドルを受け取り、それがそのままブーメラン効果
としてアメリカへの株式投資、債権投資、直接投資として循環し、空前の株ブームや
経済成長を可能にした。そして、資産バブルにより際限の無いアメリカ人の消費を
支えていたという構図である。しかし、赤字を埋める為、実体の裏づけも無く、
輪転機でドルを刷りまくれば、やがて破綻が来るのは必定である。
このあたりは国債を発行し続ける借金漬けの日本国と全く同じ構造である。
いずれにしろ、ドルの信用が失墜することをきっかけに、景気が冷え込み、
アメリカ依存の輸出国は大打撃を受け、世界経済は不況に突入するという
論証は分かりやすく、納得出来る主張である。

読んでいて果てしなく懐かしくなった。
自分は、たけしとたけし軍団とともに生きてきたんだなあとしみじみ思った。
当時、たけしの書いた本のサイン会には欠かさず行ったが、脇にはかならず軍団が控えていた。
たけしのコンサートにも行った。
コンサートの最後にそのまんま東が聴衆に向かって言う。「愛をくれ!愛をやる!」
昨日のことのようだ。
この本はたけしの歴史を振り返るとき欠かせない資料になるだろう。

子供好きの女子高生Karen ConnorsはZenner家でベビーシッター中に同家の子供の1人が行方不明になるという事件に遭遇。心当たりの有る場所へ次々に電話を掛けるが行方の手がかりさえ掴めない彼女は警察に相談を持ち込む。だが担当のRonald Wilson巡査は若過ぎるせいか教科書通りの対応しかしてくれない。そこでKarenは己の超能力という武器を用いて独自の捜査を始めるが…。本作はLois Duncan女史の1984年作であり、ヒロインのKarenがテレパシーの持ち主であるという点では異色作と言えます。しかし其のKarenのキャラクターが平凡過ぎるほど平凡である上に、肝心の誘拐ストーリーのほうも(特に終盤は)余りにも典型的な展開を辿って(しかも忙しなく)終わってしまうので、本作は女史の作品としては明らかに凡作です。

思いがけず始まった我が家の介護生活のスタートと重なり、引き込まれるように一気に読み通した。
作者の両親のようにまるで社会との繋がりを遮断している義父母のわがままを自分なりにたたみかけることができればと
考えていたが、本中の主人公の育ち方、生き方、裁判員裁判の様子を読むにつけそれまでの自分のことが少し客観的に思えてきて
むしろ本中の登場人物の方になりきっていた。
| 
